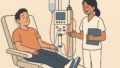今回は、血液透析患者さんの日常生活を紹介します。
現在の透析患者は34万人と減少していますが、そのうち最も多い腎代替療法は血液透析です。
2年ごとに改訂される診療報酬の方針から、国は腎ケア外来の設置によって透析導入を遅らせること、また療法選択外来の設置により腹膜透析や腎移植の腎代替療法を増やし、医療費の軽減を図ろうとしています。
ここで重要なのは、経済的な側面だけでなく、腹膜透析や腎移植のほうが患者さんの予後が良く、日常生活が維持されやすいという点です。
しかし現状では、医療者・患者双方にとって「腹膜透析や腎移植は難しそう」という印象が持たれやすい課題があります。
腹膜透析や腎移植を選択した患者さんの日常生活が気になる医療者は多いと思いますが、それについてはまた別の機会にご説明します。
まずは、血液透析患者さんの生活について触れていきます。
血液透析患者さんの生活
透析施設は、日本全国に約4,500施設あります。
冠婚葬祭や旅行などで遠方に行く場合でも、同様の医療サービスを受けることが可能です。
医療者間ではFAXや電話を使い、治療条件などの情報を共有するため、患者さんが必要書類を持参すれば、どこでも血液透析を受けることができます。
ただし、治療準備があるため、患者さん自身が希望する施設に事前に電話をかけ、空床の有無を確認し、日程調整を行うことが前提となります。
標準的な透析スケジュールは、
月・水・金 または 火・木・土 の週3回
1回の治療時間は 4時間程度
通院や治療準備、終了の時間を含めると、1回 約5時間 拘束されると考えたほうがよいでしょう。
つまり、「1回5時間の治療を週3回、一生続いていく」という認識になります。
それでも治療が足りない場合は、ECUM(限外濾過)などを追加することもあります。
また、仕事や冠婚葬祭などで予定通り透析ができない場合でも、最大で中2日しか非透析日を空けられない ため、その週は不規則な曜日で透析を行う必要があります。
日常生活では、家族や仕事、趣味など様々な予定がありますが、透析の時間を確保するために、透析スタッフと密にやり取りしながら調整していく必要があります。
そのため、透析スタッフは患者さんの生活に非常に近い存在になりますね。
透析の時間帯について
全国の透析施設では、午前透析 はほぼ全ての施設で対応しています。
しかし、午後の透析(13~16時開始) に対応していない施設もあります。
夜間(17時以降)透析 に対応している施設はさらに少なく、
オーバーナイト透析(睡眠中の透析) を実施している施設はごくわずかです。
最近では、定年の引き上げや透析治療技術の向上により、透析患者さんの中にも日中会社員として勤務している方が少なくありません。
そのため、夜間透析を希望しても満床であることが多く、施設探しに苦労する患者さんも多い です。
私の印象では、日中勤務を1時間程度早く終え、透析に通う患者さんが多い です。
非常にハードなスケジュールですね。
透析後は入浴を控える必要があるため、
「退勤 → 帰宅 → 入浴 → 通院 → 透析 → 帰宅 → 夕食 → 就寝」
という、ゆっくりする間もない日々を送っている方が多い印象です。
なんとか負担を軽減できないかと、医療スタッフとして無力さを感じることもあります。
透析患者さんの生活は千差万別
標準的な治療スケジュールはありますが、患者さんの生活パターンはそれぞれ異なります。
なぜなら、仕事・家事・育児・介護・病状など、患者さんが抱える事情や優先順位が異なる からです。
医療スタッフには、患者さんの生活を注意深く観察し、何が必要かを見極める洞察力 や、
患者さんの本音を引き出すコミュニケーション力 が求められると思います。